2012年~社会福祉士の実践力を担保する民間認定の仕組みとして認定社会福祉士制度が制定され、関係団体が参画する任意団体「認定社会福祉士認証・認定機構」が認定します。
つまり、社会福祉士は国家資格ですが、認定社会福祉士は国家資格ではありません。
認定社会福祉士
認定社会福祉士とは
2012 年から社会福祉士の実践力を担保するための民間認定の仕組みとして、認定社会福祉士制度が始まりました。認定は、関係団体が参画する任意団体「認定社会福祉士認証・認定機構」が行います。つまり、社会福祉士は国家資格ですが、認定社会福祉士は国家資格ではありません。
認定社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法の定義に定める相談援助を行う者であって、所属組織を中心にした分野における福祉課題に対し、倫理綱領に基づき高度な専門知識と熟練した技術を用いて個別支援、他職種連携及び地域福祉の増進を行うことができる能力を有することを認められた者をいう。」とされており、高齢分野、障害分野、児童・家庭分野、医療分野、地域社会・多文化分野の分野それぞれで認定されます。
認定社会福祉士になるには
認定社会福祉士になるには、次の条件を満たすことが必要です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士資格を有すること。
- 日本におけるソーシャルワーカーの職能団体で倫理綱領と懲戒の権能を持っている団体の正会員であること。
- 相談援助実務経験が社会福祉士を取得してから5年以上あり、且つこの間、原則として社会福祉士制度における指定施設および職種に準ずる業務等に従事していること。このうち、社会福祉士を取得してからの実務経験が複数の分野にまたがる場合、認定を受ける分野での経験は2年以上あること。
- 上記、実務経験の期間において、別に示す「必要な経験」があること。
- 次のいずれかの研修を受講していること。
ア 認められた機関での研修(スーパービジョン実績を含む)を受講していること。
イ 認定社会福祉士認証・認定機構が定めた認定社会福祉士認定研修を受講していること。

認定社会福祉士は、分野ごとの認定であることを押さえておいてね。社会福祉士を取得してから5年以上の相談援助実務経験ってハードル高いね。
認定社会福祉士になるまでの研修費や年会費などを含めると、10万円くらいかかるよ。しかもその後も会員になり続ける必要があるので、毎年1.5万円くらいかかるよ。
認定上級社会福祉士
認定上級社会福祉士とは
認定上級社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法の定義に定める相談援助を行う者であって、福祉についての高度な知識と卓越した技術を用いて、倫理綱領に基づく高い倫理観をもって個別支援、連携・調整及び地域福祉の増進等に関して質の高い業務を実践するとともに、人材育成において他の社会福祉士に対する指導的役割を果たし、かつ実践の科学化を行うことができる能力を有することを認められた者をいう。」とされています。
認定上級社会福祉士になるには
以下の条件を全て満たす必要があります。
2 日本におけるソーシャルワーカーの職能団体で倫理綱領と懲戒の権能を持っている団体の正会員であること
3 認定社会福祉士の認定をされていること
4 相談援助実務経験が認定社会福祉士を取得してから5年以上あり、且つこの間、原則として社会福祉士制度における指定施設および職種に準ずる業務等に従事していること。
5 上記、実務経験の期間において、別に示す「必要な経験」があること。
6 認められた機関での研修(スーパービジョン実績を含む)を受講していること。
7 定められた実績があること。
8 基準を満たした論文発表または認められた学会における学会発表をしていること。
9 試験に合格すること。
社会福祉士→認定社会福祉士→認定上級社会福祉士の順番ですね。
認定社会福祉士には試験がありませんが、認定上級社会福祉士には試験があることを覚えておきましょう。

認定社会福祉士は全国に1,000人くらいいるけど、認定上級社会福祉士は2025年現在で1人だけみたい( ̄▽ ̄)
まとめ
| 認定社会福祉士 | 認定上級社会福祉士 | |
| 活動 | ・所属組織における相談援助部門で、リーダーシップを発揮。 ・高齢者福祉、医療など、各分野の専門的な支援方法や制度に精通し、他職種と連携して、複雑な生活課題のある利用者に対しても、的確な相談援助を実践。 | ・所属組織とともに、地域(地域包括支援センター運営協議会、障害者自立支援協議会、要保護児童対策協議会等)で活動。 ・関係機関と協働し、地域における権利擁護の仕組みづくりや新たなサービスを開発。 ・体系的な理論と臨床経験に基づき人材を育成・指導。 |
| 役割 | ・複数の課題のあるケースへの対応 ・職場内のリーダーシップ、実習指導 ・地域や外部機関との窓口、緊急対応、苦情対応 ・他職種連携、職場内コーディネートなど | ・指導・スーパービジョンの実施 ・苦情解決、リスクマネジメントなど組織のシステムづくり ・地域の機関間連携のシステムづくり、福祉政策形成への関与 ・科学的根拠に基づく実践の指導、実践の検証や根拠の蓄積 |
| 分野 | 高齢分野、障害分野、児童・家庭分野、医療分野、地域社会・多文化分野 | 自らの実践に加え、複数の分野にまたがる地域の課題について実践・連携・教育 |
過去問
第28回 問題95
認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 認定社会福祉士制度の必要性は、2000年(平成12年)の社会福祉事業法改正時の附帯決議に盛り込まれた。
2 認定社会福祉士は、所属組織以外の分野における高度な専門性を発揮できる能力を有する者として位置づけられている。
3 認定社会福祉士は、一定の実務経験と認定試験に合格することが要件とされている。
4 認定上級社会福祉士は、高齢分野、障害分野、児童・家庭分野、医療分野など、分野ごとに認定される。
5 認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士は、関係団体が参画する組織によって認定される。
1 認定社会福祉士制度の必要性は、2000年(平成12年)の社会福祉事業法改正時の附帯決議に盛り込まれた。
間違いです。認定社会福祉士の必要性は2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正時の附帯決議に盛り込まれています。
2 認定社会福祉士は、所属組織以外の分野における高度な専門性を発揮できる能力を有する者として位置づけられている。
間違いです。所属組織以外の分野ではなく、所属組織を中心にした分野における福祉課題に対し、倫理綱領に基づき高度な専門知識と熟練した技術を用いて個別支援、他職種連携及び地域福祉の増進を行うことができる能力を有することを認められた者とされています。
3 認定社会福祉士は、一定の実務経験と認定試験に合格することが要件とされている。
間違いです。試験の合格は要件ではありません。認定上級社会福祉士は試験の合格が要件です。
4 認定上級社会福祉士は、高齢分野、障害分野、児童・家庭分野、医療分野など、分野ごとに認定される。
間違いです。認定上級社会福祉士ではなく認定社会福祉士の内容です。
5 認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士は、関係団体が参画する組織によって認定される。
正しいです。関係団体が参画する組織とは「認定社会福祉士認証・認定機構」です。
第27回 問題91
2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。
2 社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
3 判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。
4 地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。
5 認定社会福祉士の規定が設けられ、高度な福祉ニーズに的確に応えることのできるより専門性の高い人材を確保することが明記された。
1 業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。
間違いです。このような内容は法には書かれていません。
2 社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
これが正解です。
3 判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。
間違いです。このような規定はありません。
4 地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。
間違いです。ボランティアへの助言や指導は社会福祉士の定義として明記されていません。
5 認定社会福祉士の規定が設けられ、高度な福祉ニーズに的確に応えることのできるより専門性の高い人材を確保することが明記された。
間違いです。認定社会福祉士は法的には規定されていません。
第37回 問題110
認定社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 地域や外部機関との対応窓口、他職種との連携よりも、所属機関の機能に応じた社会福祉専門職としての高度な支援を行うことが求められる。
2 地域共生社会の実現に向けて求められるより高度な知識や技術等は、認定社会福祉士制度などを通して、継続して学ぶことが望まれる。
3 スーパービジョンの実施にあたっては、スーパーバイザーとスーパーバイジーの両者が、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範を遵守しなければならないと定められている。
4 認定社会福祉士を取得するには、社会福祉士として20年以上の相談援助実務経験があることが要件とされている。
5 社会の変化とニーズの多様化・複雑化に対応するため、10年に一度の更新が求められる。
1 地域や外部機関との対応窓口、他職種との連携よりも、所属機関の機能に応じた社会福祉専門職としての高度な支援を行うことが求められる。
誤りです。他職種との連携より高度の支援が優先ということはありません。
2 地域共生社会の実現に向けて求められるより高度な知識や技術等は、認定社会福祉士制度などを通して、継続して学ぶことが望まれる。
正しいです。
3 スーパービジョンの実施にあたっては、スーパーバイザーとスーパーバイジーの両者が、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範を遵守しなければならないと定められている。
正しいです。
4 認定社会福祉士を取得するには、社会福祉士として20年以上の相談援助実務経験があることが要件とされている。
誤りです。20年以上ではなく5年以上です。
5 社会の変化とニーズの多様化・複雑化に対応するため、10年に一度の更新が求められる。
誤りです。認定審査の合格日の翌年度の4月1日から5年ごとに更新しなければならないとされています。
次の記事
次は、スクールソーシャルワーカーと医療ソーシャルワーカーについて。

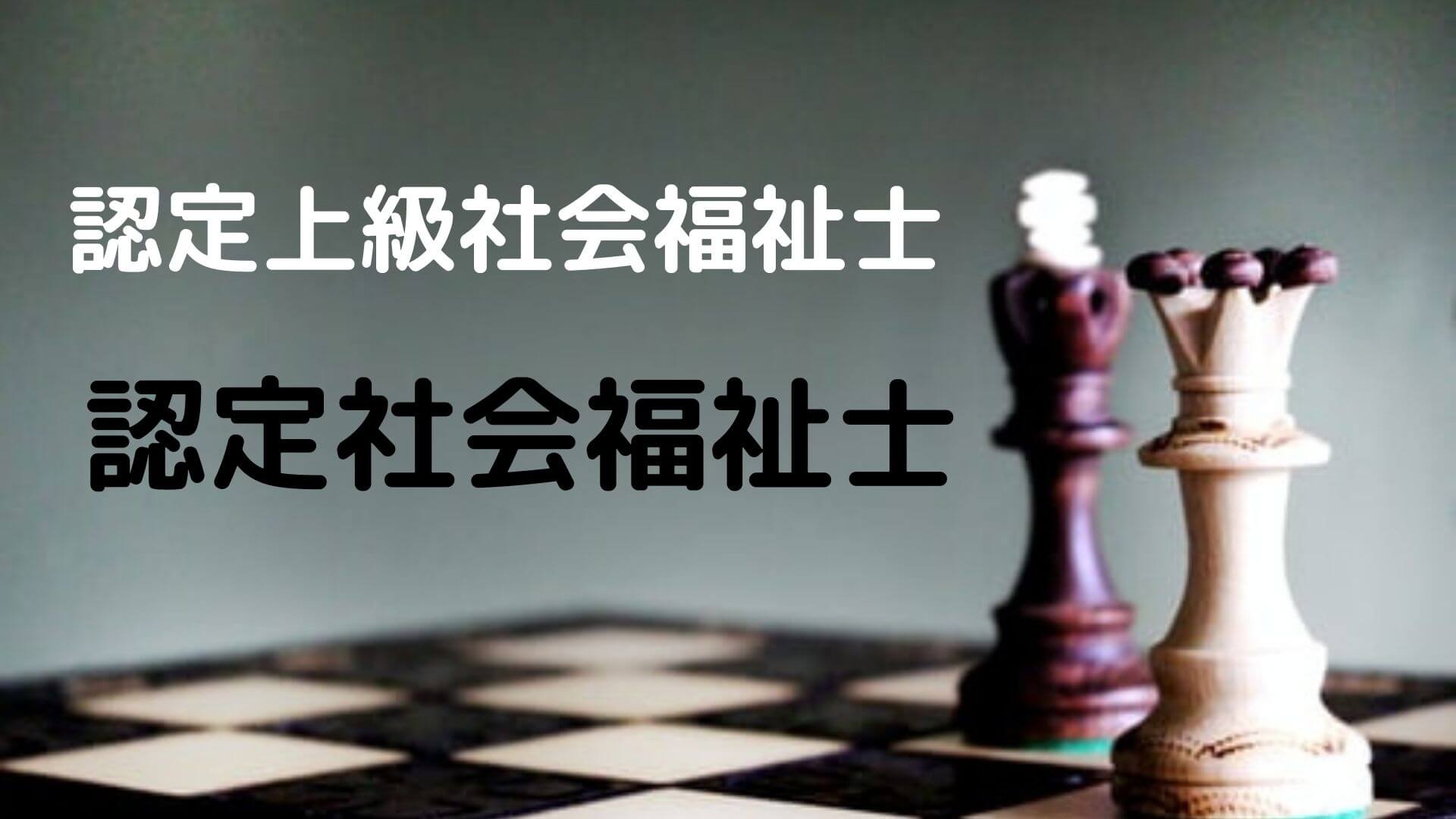


コメント