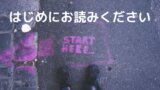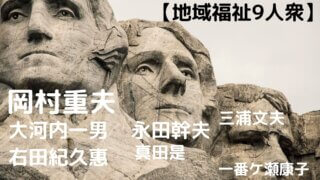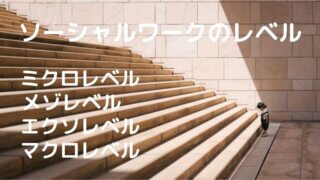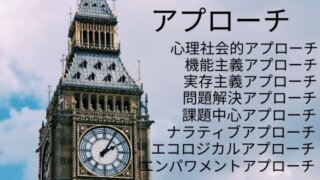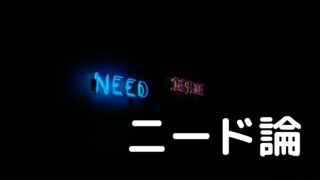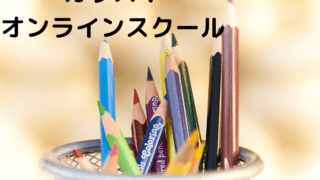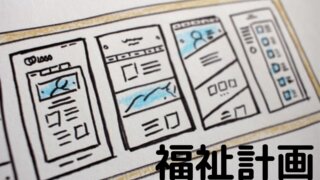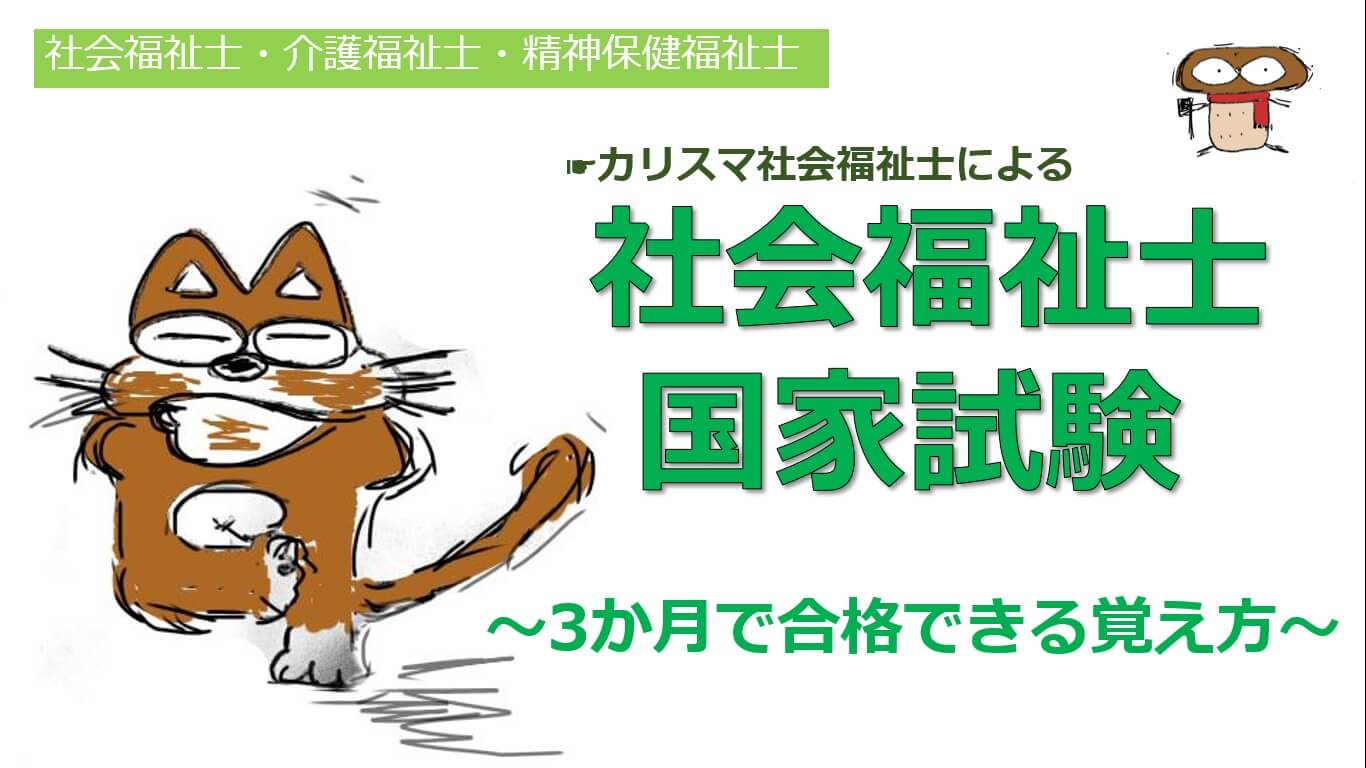社会福祉士国家試験を目指す中で、こんな悩みを抱えていませんか?
・勉強の仕方がわからない
・いくら勉強しても感触がない
・過去問を解くのにやたら時間がかかる
・受かる気がしない
国家試験対策として様々な教材がありますが、大手の参考書は事実が羅列してあるだけでぜんせん頭に入らないし、大手予備校の講座は高額な上に難しくて分かりにくいし、YouTube動画を見てもついていって良いのか怪しいし・・・。
結局、体系的かつ分かりやすく学べるモノがないので、これで合格できるのかと不安になるのが社会福祉士国家試験受験生の多くの悩みです。
当ブログは上記のような悩みを全て解決するために、管理人であるカリスマ社会福祉士が受験生の立場で、3カ月で合格できる学習方法を提供するものです。
このブログは、これから社会福祉士を目指す人に向けて、次の3つを達成できるように構成しています。
1.社会福祉士国家試験に向けて辛い勉強を少しでも楽しい時間にする
2.確実に合格するための知識と思考力が身につく
3.社会福祉士になってから仕事で役立つホンモノの知識を習得する
精神保健福祉士(専門科目のみ)を目指す方はこちら。
介護福祉士を目指す方はこちら。
社会福祉士を目指す方へ
受験生には、このブログの全ての記事を読み込めば、国家試験に合格できるように作ってあります。
当ブログを利用して1カ月で合格した方も出ました。
過去に不合格だった方は、「あのとき不合格でよかった、このブログに出逢えてホンモノの知識が身に付いたから」と思ってもらえるよう、内容は相当作り込んでいます。
学習関連の記事は全部で150記事ほどあり、それらは出題分野を網羅し、各分野でどのように覚えれば効率がよいのかを考えて構成してあります。
例えば、歴史であれば流れを学ぶことで記憶に定着しやすくなりますし、各論であれば過去問をたくさん解くことが理解への近道になります。
まずは以下の「社会福祉士国試 学習方法指南」を読んでください。
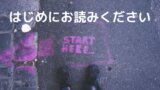
【社会福祉士国家試験】学習方法指南
社会福祉士国家試験を目指す中で、こんな悩みを抱えていませんか?・勉強の仕方がわからない・いくら勉強しても感触がない・過去問を解くのにやたら時間がかかる・受かる気がしない
国家試験対策として様々な教材(出版物、講座、Youtube動画)などがありますが、大手の参考書は事実が羅列してあるだけでぜんせん頭に入らないし、大手予備校の講座は高額な上に難しくて分かりにくいし、Youtube動画を見ても本当についていって良いのか怪しいし・・・。結局、体系的かつ分かりやすく学べるモノがないので、これで合格できるのかと不安になるのが社会福祉士国家試験受験生の多くの悩みです。
記事の下に次に読んでほしい記事が張り付けてありますので、その順序に沿って記事をどんどん読んでいけば、効率よく学習できるように道筋を作ってあります。
新着記事を配信した時は、X(旧 twitter)で告知しています。
記事を読んだ後に、講義動画を見て知識を定着させるようにしてください。
以下のYouTubeチャンネルを登録すれば、講義動画は見放題です。
![]()
カリスマ社会福祉士
社会福祉士国家試験を目指す中で、こんな悩みを抱えていませんか?・勉強の仕方がわからない・いくら勉強しても感触がない・過去問を解くのにやたら時間がかかる・受かる気がしないそんな悩みをカリスマ社会福祉士が全て解決します。カリスマ社会福祉士は、現...
社会福祉士として働く方へ
このサイトは社会福祉士国家試験の受験者のために特化して作ったのですが、今では福祉で働くすべての人に学んでほしい内容となっています。
現在、社会福祉士として働く方には、身に着けてほしい知識を網羅しておりますので、おそらく一度は国家試験受験勉強で学んだ内容かと思いますが、ぜひ読んでみてください。
社会福祉士として働く方へ、読んでほしい記事を載せておきます。

【ナチス強制収容所の地獄を生きた3人】コルチャックの人生に涙
社会福祉士・介護福祉士の受験勉強をしながら、この3名の偉人を知れたことは幸せでした。社会福祉士を目指す全ての人に知ってほしい3名を紹介します。ナチス強制収容所の地獄を生きた3人「ノーマライゼーションの父」バンク-ミケルセンノーマライゼーショ...
新カリキュラムへの対応
2024年度から社会福祉士国家試験には新カリキュラムを反映させた問題が出題されます。
ブログ記事とYouTube動画は、全て新カリキュラム対応済みなのでご安心ください。
サイト管理人プロフィール
サイト管理人

現役の社会福祉士として働きながら、社会福祉士受験指導のプロとして活動。3カ月で確実に国家試験に合格できる「講義」が好評。
はじめまして。障害福祉の世界で働き始めて15年、カリスマ社会福祉士です。普段は、障害のある人たちの援助をしながら、社会福祉士を目指す方々に受験指導をしています。
プロフィール写真は保護猫のシロです。
シロは、小さいころに虐待を受け、片足がありません。
白血病も患っていて、保健所ではこのような病気や障害のある猫は引き取り手がいません。子猫は人気があって順番待ちなのに。
しかも、たとえ引き取り手がいても病気があれば必ず殺処分されます。
人間の世界でも、動物の世界でも、障害や難病というのは、手厚い支援が必要なのに行き届いていないという現実。そんな苦しみを抱える人や動物の幸せに少しでも貢献できたらと思いながら生きています。人間のせいで不幸になってしまった動物たちに、少しでも幸せを感じてもらえるように。シロは、障害も病気もありますが、カリスマ社会福祉士と出会い、毎日元気に走り回っております。
<経歴>
2003年京都大学工学部物理工学科卒
2005年京都大学大学院エネルギー科学研究科卒
卒業後は電機メーカーに就職するが3年で退社し福祉の道へ。
<資格>
・介護福祉士国家資格(125点/125点、実技試験も合格)
・社会福祉士国家資格(117点/150点)
・公認心理師国家資格(156点/230点)
・精神保健福祉士国家資格(71点/80点)
・危険物取扱者免状(乙種4類)
・有機溶剤作業主任者
・特定化学物質等取扱主任者
・特定高圧ガス取扱主任者
・特殊高圧ガス取扱主任者
・プロボクサーライセンス